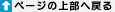言語聴覚科の役割
言語聴覚療法では、様々な原因でことばやコミュニケーションに障害がある方に対して、まず、必要な検査や評価を行います。それに基づいて訓練を行い、本人様やご家族に対して必要となる助言・指導を行い、自分らしい生活を構築できるように支援していきます。
訓練の内容
失語症
失語症とは、脳卒中や事故などにより大脳の言語中枢が損傷される事で起こる「聴く」「話す」「読む」「書く」と言ったことばの機能の障害であり「ことばが出にくい」「相手の言っていることが分からない」などの問題が生じます。
日常よく使うことばを絵カードや文字カードにして、発語や聴き取りの訓練を行ったり、ことばをうまく伝えることができない場合には指差しやジェスチャー、描画などを用いたコミュニケーション手段の獲得のための訓練を行います。

構音障害
構音障害とは、発声・発語に必要な期間(唇・舌)の麻痺により、ろれつが回らなくなったり声が小さくなったりすることで、ことばが不明瞭になる障害です。
唇や舌などの運動訓練(例えば唇を「ウーッ」と尖らせたり「イーッと横に引く運動」)を行ったり、発声・発音訓練(ゆっくりはっきりと発音できるように指導)などを行います。
摂食・嚥下障害
摂食・嚥下障害とは、唇や舌、ノドの麻痺などにより食べること・飲み込むことが難しくなる障害です。うまく噛むことができなかったり、食べ物や飲み物でムセてしまったりします。
間接的嚥下訓練では、食べ物を使わず唇や舌の運動訓練をしたり、冷たい刺激をつかって飲み込む訓練などを行います。また直接的嚥下訓練では、飲み込みの状態に合わせてゼリーやトロミ付の水分、形態を考慮した食事など、実際に食べ物を用いて安全に飲み込む力をつける訓練を行います。